内申で合否が決まる
内申点は、君らが私立を志望しようが、公立を志望しようが絶対的に必要になってくるものです。
前期で紹介しまくっていた難関私立の推薦入試では内申があることがそもそもの受験資格になります。
公立高校の入試では、1・2年生からの内申点も当日の点数に加算されます。
高校受験において、たとえ合格する力を持っていたとしても、内申点のせいで不合格になることもありますし、実力が“多少”なくても内申点のおかげでカバーできることもあります。
内申点は、大きな武器になることも、足かせになることもありうるということを、肝に銘じておくようにしましょう。
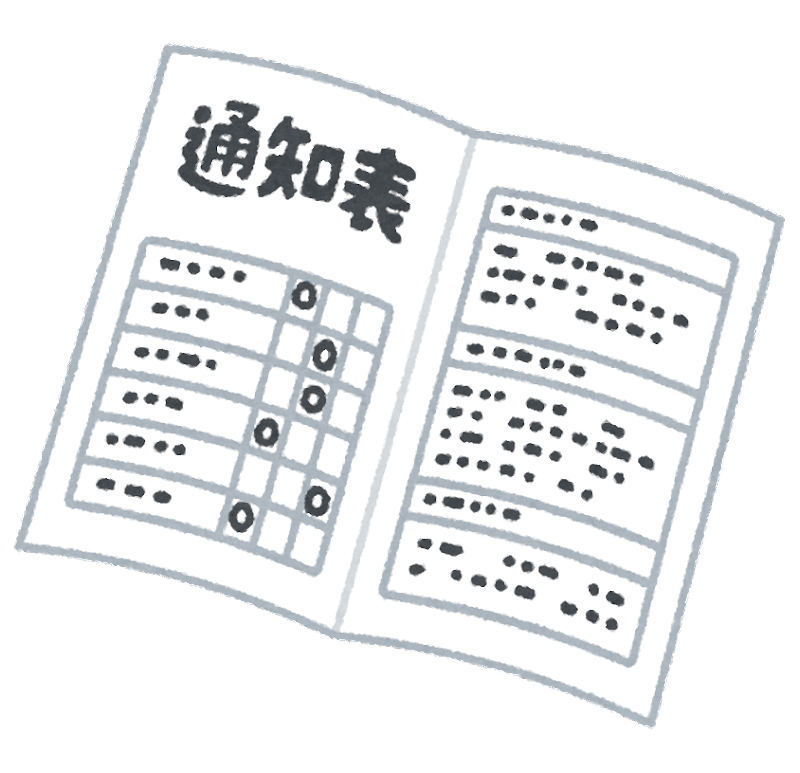
他者から見て、自分はどう映っているか(=メタ認知)
内申は、学校の先生がつけるものです。相手は人なので、学校の方針や先生の好みによって評価が左右されてしまうことがでてきてしまいます。
そのシステムの賛否は、君たちの中にもあることでしょう。
しかし、学校の先生がつける評価に不満がある人は、その人自身にも問題がある場合がほとんどです。
「定期テスト80点取ったのに3だった」「提出物ちゃんと出したのに3だった」という不満をよく聞きますが、普段の授業の確認テストである定期テストで80点取ることは、すごいことではない。提出物を出すことも、当たり前ですよね。
内申点に不満がある人は、自分で自分の評価をしているにすぎません。
当然、理不尽な先生もいるでしょうが、文句を言っても先生が変わることはないのですから、自分がどう変わろうかと考える方が健全です。
あくまで評価するのは学校の先生。
内申に必要なのは、「他者から見て、自分はどう映るかという意識」です。
この意識を、心理学の言葉でメタ認知といいます!
さて、1学期を振り返り、自分をメタ認知してみましょう。
また、内申点「3」というのは、「普通、平均」という意味ではありません。ここで5段階の各評定に対して、先生が思っていることを書いておきます。
5→「頑張っているな~、クラスにいて欲しい。結果も優秀。文句なし!!」
4→「意欲的に参加してるな、クラスにいて欲しい。けどテストor提出物はもう少し頑張って欲しいな。」
3→「この子どうだったけ。。。テストも低すぎず高すぎない、、、提出物は出しているか、、、うーん、3!!」
2→「できればクラスにいて欲しくないんだよな~。テストor授業態度もよくないし。」
1→「正直クラスにいて欲しくない。テストや授業態度も最悪。もはや迷惑。(不登校の場合は例外)」
注目してほしいのは“3”です。
学校の先生は毎日何百人に授業をしていて、学期末に何百人の評定をつけます。
その時、印象に残ってない生徒は“3”に位置づけされるでしょう。つまり、残酷な言い方をすれば“3”という評価は「いてもいなくても変わらない」存在ということです。
いい印象に残れば、3より上になります。
そして、進路に関わることも先生はわかっていますので、テストが平均点前後の点数は取れていて、提出物が出せていれば、よっぽどのことがなければ1や2はつけません。
なので、むしろ3が一番下ぐらいの感覚でいた方がいいかもしれませんね。(もちろん、すべての事象に当てはまるわけではありません。)
堂々と内申点を稼ぎにいくべし
【内申を稼ぐという行為】は、主に以下の4つです。
①小テスト・定期テストを頑張る
→勉強の仕方そのもの。受験勉強に直結すること。
②提出物をちゃんとやる
→期限を守る、丁寧にやる社会生活のベースとなること。
③授業を聞く
→人の話をちゃんと聞くというコミュニケーションの基本中の基本。(人の話を寝るなんて論外ですよね?)
④発言する
→自分の主張、考えを相手に伝えるという基本行為
(最初にも書いた通り、好みだろ!というような内申をつけられるときもたまにあります。が、ほとんどがその子に問題がある場合が多いです。)
内申を稼ぎに行く行為は、君たちが大人になっていく中で重要な基本行為、相手の立場に立ち、他者意識を育む、訓練だと思ってください。
埼玉の私立高校の1部は、内申点だけで合格のお約束がもらえるところもあります。
いいか悪いかはおいておいて、、、
内申点が高い人は、それだけ人としてのベースができているということであり、その子の学力を度外視しても、その姿勢が出来上がっている人は高校側からも必要とされる存在というわけです。内申点と学力には、ある程度の相関関係はあります。
せこいとか、卑怯だなんて思わないでください。本番の入試で頑張るとか言って逃げないでください。
正々堂々、内申点を稼ぎにいきましょう。
